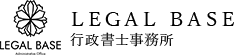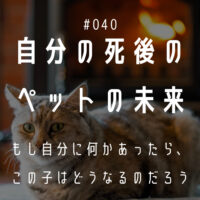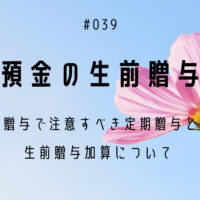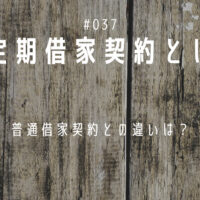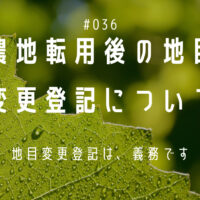#014『未登記物件の相続』
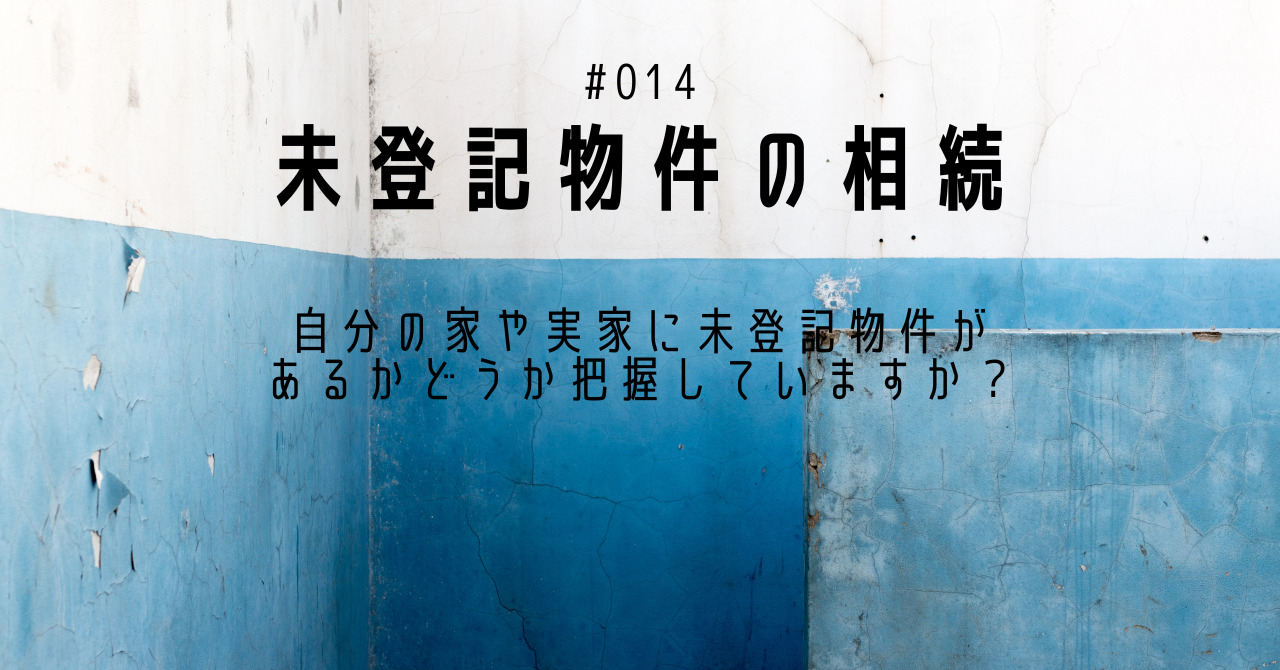
未登記物件の相続は少し特殊!対応や選択肢を解説します
目次
未登記物件とは? 相続前に知っておくべき基本
LEGAL BASE代表のSanukiです。
相続が発生した際、遺産の中には「未登記物件」と呼ばれる特殊な不動産が含まれていることがあります。これは、法務局の不動産登記簿に登記されていない建物を指します。通常、建物が新築されたり、増築されたりした場合には、所有者が登記を申請する義務がありますが、何らかの理由でこの手続きがされていない建物が世の中には数多く存在します。
例えば、昭和以前に建てられた古い家屋、増築部分が登記されていない建物、あるいは個人や大工さんが建てた倉庫・車庫などが未登記物件に該当する可能性があります。固定資産税の課税台帳には載っていても、公的な登記簿には記録がない状態、と考えると分かりやすいかと思います。
なぜ未登記物件が存在するのか?
未登記物件が存在する背景には、いくつかの要因が考えられます。
- 昔の慣習や知識不足: 不動産登記の重要性が今ほど認識されていなかった時代には、登記せずに建物を使用することが一般的でした。特に建築当時、地元の大工さんに建ててもらった場合で現金で工事代を払っているようなケースでは登記がされていないことが多いです。大工さんは家を建てるまでが仕事でその後の手続までは把握はしていないという方が多かったのかもしれません。
- 手間と費用の問題: 登記には登録免許税や専門家への報酬などの費用や手間がかかるため、経済的な理由や煩雑さから登記を避けたケースもあり得ます。
- 増築部分の登記漏れ: 既存の建物に増築を行ったものの、その部分の変更登記を忘れてしまった、あるいは意図的に行わなかったケースもよく見られます。
未登記物件を相続する際のリスクと注意点
未登記物件を相続することは、以下のようなリスクがあります。
- 所有権の証明が難しい
登記は、その不動産の所有者が誰であるかを第三者に公示する強力な効力(対抗力)を持ちます。未登記の場合、法的には所有者であっても、第三者に対してその所有権を明確に主張することが難しくなります。例えば、建物の売買や賃貸借を行う際に、所有権の証明が求められると、手続きが滞る可能性があります。
- 資産活用や売却が困難
未登記物件は、金融機関が担保として評価しないため、融資を受ける際の担保にすることができません。また、所有権が不明確なため、売却しようとしても買い手が見つかりにくいという可能性もあります。買い手側からすれば、将来的なトラブルや追加費用のリスクを避けたいと考えるのが自然であるためです。
- 相続税評価や遺産分割が複雑になる可能性
未登記物件であっても、相続税の課税対象となります。市町村によって固定資産評価はされているものの、登記情報がないため、正確な評価が難しく相続税の申告で手間や時間がかかる可能性があります。また、複数の相続人がいる場合、未登記物件の評価や分割方法を巡って意見が対立し、相続人同士の争いに発展する可能性も否定できません。
未登記物件の相続における選択肢
未登記物件を相続した場合、大きく分けて2つの対応が考えられます。
- 登記を完了させて相続する方法(建物表題登記+所有権保存登記)
最も良いのは、未登記の状態を解消し、正式に登記を行うことです。これにより、所有権が明確になり、将来的なトラブル発生のリスクを抑えることができます。そもそも不動産登記法では、表題登記については建築から1ヵ月以内の登記義務が課せられているので、法的には未登記状態というのは「違法」となります。
ただし登記されずに放置されている未登記物件は多数存在し、行政側もわざわざ「違法」ということで制裁まで課しているケースはおそらくあまり無いかと思います。ただ、近年は、法改正により不動産の所有権に関する登記が義務化される流れが進んでいるため、未登記物件を放置すると何らかの制裁リスクは今後高くなると言えます。
登記する場合、まず「建物表題登記」を行います。これは、その建物が登記簿にまだ登録されていない場合に、建物の物理的な情報(所在地、種類、構造、床面積など)を新たに登記簿に記載する手続きです。この建物表題登記の申請人は、原則として相続人となりますが、図面などが必要で専門性が高いため、個人での申請はまず無理だと思います。代理で依頼する場合は、土地家屋調査士の業務となります。
建物表題登記が完了し、登記簿に建物が登録されたら、次に「所有権保存登記」を行います。この登記によって、その建物の最初の所有者が誰であるかが登記簿に記録され、公的に所有権が認められます。未登記物件の相続においては、この所有権保存登記を相続人自身の名義で申請します。この業務は代理で依頼する場合は、司法書士の業務となります。
登記手続きが完了することで、相続人は未登記物件の所有権を法的に確立し、安心して不動産を所有・活用できるようになります。
- 未登記のまま市町村へ届出を行う方法
登記を行わず、市町村に対して「未登記家屋の所有者変更届(※書類の名称は市町村によってまちまちです)」などを提出し、固定資産税の納税義務者を変更する方法もあります。この手続きにより、市町村の固定資産税台帳上の未登記物件の所有者が被相続人(亡くなった方)から相続人へと変更され、相続人が適切に固定資産税を納めることができるようになります。こちらは、届出を代理で依頼する場合は、行政書士の業務となります。
ただし、先程お伝えした通り登記をしないことは、法令上のリスクもありますし、所有権の第三者に対する公的な証明にはなりません。将来的な売却なども視野に入れている場合は、改めて登記手続が必要になる可能性があります。
未登記物件の相続をスムーズに進めるためにすべきこと
- 早期の専門家への相談
未登記物件の相続は、通常の相続よりも判断が難しい場合があります。相続が発生したら、早めに専門家(行政書士、司法書士、土地家屋調査士)に相談するのが良いでしょう。
- 相続人全員での情報共有と協力
未登記物件の取り扱いについては、相続人全員で情報を共有し、協力体制を築くことが重要です。特に、登記を行うか、あるいは市町村への届出で済ませるかなど、今後の対応について合意形成を図っておくことで、後のトラブルを避けることができます。
- 固定資産税の納税状況の確認
未登記物件であっても、課税の要件を満たす建物であれば原則として固定資産税が課税されています。納税義務者が誰になっているか、滞納がないかなどを確認し、必要であれば市町村の担当部署に問い合わせてみましょう。
- 将来的な売却や活用の意向を考慮する
その未登記物件を将来的に売却する予定があるのか、あるいは賃貸するなどして活用したいと考えているのかによって、取るべき対応は変わってきます。売却や活用を視野に入れているのであれば、登記を完了させる方が賢明な選択と言えるでしょう。ご両親が亡くなった後の自宅をどうするのか、早めに法定相続人間で話し合っておきましょう。
まとめ:未登記物件の相続は把握と専門家への相談がより大事
未登記物件は、手続をするうえで、手続きがスムーズに行かない、時間や費用が掛かる1つの理由になり得ます。ご自身だけで判断せずまずは専門家に相談しましょう。当事務所では、相続に関するご相談を随時受け付けております。お客様の状況に合わせて、メリット・デメリットや市町村への届出の有効性、司法書士や土地家屋調査士のご紹介などを含め、具体的なアドバイスを提供させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
LEGAL BASE行政書士事務所|先を見据えた戦略を
https://www.office-legal-base.jp/
Open base|note
https://note.com/openbase