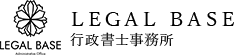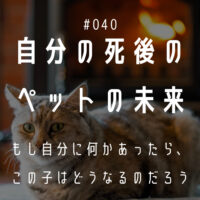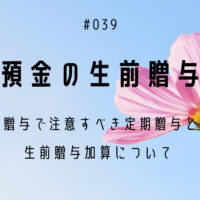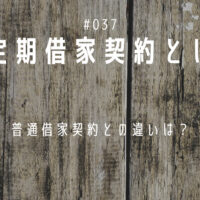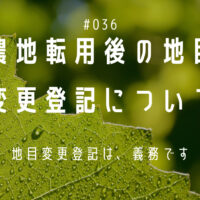#011『孤独死と賃貸借』

相続放棄をすれば原状回復義務はなくなる?相続の専門家が徹底解説
目次
「身内が賃貸アパートで孤独死してしまった…。」
「部屋の片付けや高額な請求が来たらどうしよう…。」
「相続放棄をすれば、すべての責任から解放されるの?」
突然の不幸に見舞われ、このような不安を抱えている方は少なくありません。高齢化社会が進行する現代において、孤独死は誰にでも起こりうる身近な問題です。
こんにちは、福岡・博多駅徒歩1分の行政書士事務所 『LEGAL BASE』 代表のSanukiです。
この記事では、孤独死が起きた賃貸物件の「賃貸借契約」と「原状回復義務」が法的にどう扱われるのか、そして「相続放棄」がどのような影響を及ぼすのかを解説します。
1.孤独死発生…まず知るべき「賃貸借契約」の相続
- 賃貸借契約は相続人に引き継がれるのが原則
まず最も重要な点は、賃貸物件の借主が亡くなっても、賃貸借契約は自動的に終了しないということです。借主が持つ「部屋を借りる権利(賃借権)」と、それに伴う「家賃の支払い義務」や「原状回復義務」などの権利義務は、原則として法定相続人に引き継がれます。
つまり、相続人は故人(被相続人)に代わって、大家さん(貸主)との契約関係を続けるか、あるいは解約するかの選択を迫られることになります。
- 相続人が負う具体的な義務
相続人が引き継ぐ主な義務は以下の通りです。
|
2.孤独死の「原状回復」はどこまで?費用の内訳と相場
原状回復とは、単に部屋を掃除するだけではありません。孤独死のケースでは、通常の退去とは異なる特別な対応が必要となり、費用も高額になりがちです。
2-1. 国土交通省のガイドラインが示す基本
原状回復の範囲については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が基準となります。
|
孤独死による部屋の汚損や腐敗は、後者の「借主の故意・過失」に準ずる「特別な損耗」として扱われるのが一般的です。
2-2. 孤独死で発生する特別な原状回復費用の内訳
具体的には、以下のような費用が発生します。
|
(1)特殊清掃費用: ご遺体の発見が遅れると、体液による汚損や腐敗臭が床や壁に染み付いてしまいます。これを原状に戻すには、専門業者による「特殊清掃」が不可欠です。消臭・消毒・害虫駆除などが行われ、状況によっては壁紙や床材の張り替えも必要になります。
(2)残置物(遺品)の撤去費用: 故人が残した家具や家電、生活用品などの「残置物」をすべて撤去する費用です。相続人が自ら行うことも可能ですが、量が多い場合や遠方に住んでいる場合は、遺品整理業者に依頼するのが一般的です。
(3)逸失利益(損害賠償): 孤独死があった物件は「事故物件」となり、次の入居者が見つかりにくくなったり、家賃を下げざるを得なくなったりします。この”大家さんが得られたはずの利益(逸失利益)”を、損害賠償として請求されるケースがあります。
|
3.相続放棄をすれば、義務から完全に逃れられるのか?
多額の負債や原状回復費用を前に、「相続放棄」を検討する方は多いでしょう。しかし、ここには重要な注意点があります。
3-1. 相続放棄の基本的な効果
家庭裁判所で相続放棄の手続きが受理されると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。これにより、故人のプラスの財産(預貯金、不動産など)も、マイナスの財産(借金、各種義務など)も、一切引き継ぐことがなくなります。
つまり、相続放棄をすれば、原則として未払い家賃の支払いや原状回復義務、損害賠償義務を負うことはありません。
3-2. 注意!相続放棄をしても「管理責任」が残る場合がある
ここで安心してはいけません。2023年4月の民法改正により、相続放棄後のルールが明確化されました。
|
改正民法 第940条1項 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。 |
簡単に言うと、「相続放棄をしても、その財産(この場合は賃貸物件)を事実上管理できる状態にあるならば、次の管理者が決まるまで、最低限の管理をしなさい」という責任が残るのです。
例えば、相続人全員が相続放棄をした場合でも、故人の部屋の鍵を持っているなど「現に占有している」相続人は、大家さんや後述する「相続財産清算人」に部屋を引き渡すまで、部屋が勝手に荒らされたりしないように管理する責任を負う可能性があります。
この「管理責任」を怠って損害が拡大した場合、大家さんから損害賠償を請求されるリスクがゼロではありません。
ただし、これは「現に占有している」相続人の話であり、全く物件に関与していない相続人については、管理責任を問われる可能性は低いと思われます。
3-3. 最終手段としての「相続財産清算人」の選任
相続人全員が相続放棄をし、かつ誰も管理をしたくない場合、大家さんなどの利害関係者は家庭裁判所に「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」の選任を申し立てることができます。
相続財産清算人は、弁護士などの専門家が選ばれ、故人の財産(預貯金など)を使って部屋の原状回復や各種支払いを清算し、最終的に賃貸借契約を解約します。
- メリット: 相続人は法的に一切の義務から解放されます。
- デメリット: 選任には予納金として数十万円~100万円程度の費用がかかる場合があります。この費用は故人の財産から支払われますが、財産が足りなければ申立人(大家さんなど)が負担することになります。
4.相続放棄を検討する際の重要ポイント
4-1. 遺品整理は慎重に!「法定単純承認」に注意
相続放棄を考えている場合、故人の財産を勝手に処分してはいけません。価値のある遺品を売却したり、預貯金を引き出して使ったりすると、「相続する意思がある」とみなされ(法定単純承認)、相続放棄ができなくなる可能性があります。
ただし、形見分けとして写真や手紙など、財産的価値のないものを持ち帰る程度であれば問題ありません。判断に迷う場合は、手を付ける前に専門家に相談しましょう。
4-2. 相続放棄の期限は「3ヶ月」
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。この期間は意外と短いため、孤独死の対応に追われているうちに過ぎてしまうことも少なくありません。必要であれば、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。
4-3. 「連帯保証人」の責任は消えない
故人が賃貸借契約を結ぶ際に「連帯保証人」を立てていた場合、注意が必要です。相続人が相続放棄をしても、連帯保証人の責任はなくなりません。
大家さんは、相続人に請求できない未払い家賃や原状回復費用を、連帯保証人に請求することになります。ご自身が連帯保証人になっている場合はもちろん、他の親族がなっていないかも確認が必要です。
5.まとめ:孤独死の相続問題は、一人で抱え込まず専門家へ
孤独死が起きた賃貸物件の相続は、法的な知識と複雑な手続きが絡み合い、精神的にも経済的にも大きな負担となります。
|
ポイント |
内容 |
|
契約の相続 |
賃貸借契約は相続人に引き継がれる。未払い家賃や原状回復義務も相続の対象。 |
|
原状回復の範囲 |
特殊清掃、残置物撤去、損害賠償(逸失利益)など、高額になる可能性がある。 |
|
相続放棄の効果 |
原則として、すべての義務から解放される。 |
|
相続放棄の注意点 |
①相続放棄後も「管理責任」が残る場合がある ②遺品整理は慎重に(法定単純承認のリスク) ③期限は3ヶ月 ④連帯保証人の責任は消えない |
ご自身の状況で「相続すべきか、放棄すべきか」「原状回復費用は妥当か」といった判断に迷ったら、一人で抱え込まずに、なるべく早く相続問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。突然の不幸に冷静な判断は難しいものですが、適切な知識とサポートを得て、一歩ずつ着実に問題解決へ進んでいきましょう。
LEGAL BASE行政書士事務所|先を見据えた戦略を
https://www.office-legal-base.jp/
Open base|note
https://note.com/openbase