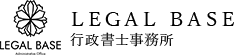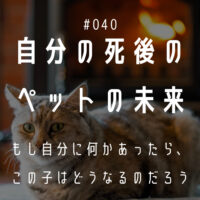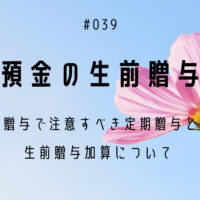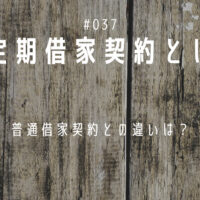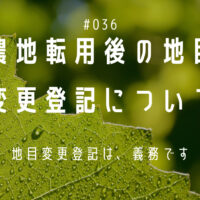#010『相続土地国庫帰属制度』

福岡・博多駅徒歩1分の行政書士事務所 『LEGAL BASE』 代表のSanukiです。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
義務化についての詳細は、前回記事に書いておりますので、良ければご覧ください。
今回は、相続した不動産を不要で手放したい場合に、国に引き取ってもらう『相続土地国庫帰属制度』という制度について、概要と注意すべき点などについて説明します。
相続土地国庫帰属制度
1.相続土地国庫帰属制度とは
まず、相続土地国庫帰属制度の趣旨についてですが、法務省のサイトより抜粋します。
|
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始しています。
|
法務省WEBサイトより
簡単に言うと、相続等により取得した土地が不要な場合に国に引き取ってもらう制度です。この背景には、前回の記事「相続登記の義務化について」で書いたとおり、所有者不明土地が増えることを抑制したいという国の意図があります。
「管理できない土地を相続で取得する」ということは、結局、将来的にその人が更に亡くなる二次相続が起きたときにも、次の世代へ土地の管理が引き継がれない可能性が高いといえます。
相続人の方から「土地の管理ができない。」「土地要らないんだけどねぇ。」と言った声をよく聞きます。
売却ができるような土地であれば、「売る」という選択を取れば良いと思います。当然、皆様一度はそのように考えられるでしょう。
しかしながら、都市部以外の地域ではどこも少子高齢、人口減少の流れなので、土地の需要は少なく、いわゆる「売れる土地」というのは、限られています。
地方に住まれている方は、土地を数十筆持たれている方も珍しくはありません。特に農家の方は、田畑や山林、原野を多く所有しています。これらの多くの土地は、広すぎたり、逆に小さすぎたり、土地に至る為に他人の土地を通る必要があったり、売却には不向きな土地です。また、そもそも田や畑は、農地法の規制があるため、農業者に対してではないと譲ることができません。
では、こういった土地を国が全部引きとってくれるのかと言われると、必ずしもそうではありません。残念ながら、国庫帰属制度で引き取ることができる土地も様々な条件があります。
2.引き取ることができない土地
では、引き取ることができない、国庫への帰属ができない土地についてみてみます。こちらは、具体例が法令で定められています。
(1)建物の存する土地
建物は、管理コストが高額であることや、最終的には建替えや取り壊しが必要になるため、建物が建っている土地は、国庫帰属の申請ができません。どうしても申請したい場合、建物を取り壊す必要があります。その場合でも、取り壊した後に引き取って貰えそうか、必ず事前に相談をしましょう。
(2)担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
担保権とは、抵当権や地上権といわれる第三者の権利のことです。銀行から借り入れをする場合、土地を担保として提供することがありますが、そういった場合に付けられる権利が「抵当権」です。ローンの返済が完了していれば、担保権を外すことができます。
そのほか、地上権や地役権、賃借権などの第三者の権利が土地に対して存在する場合、国が引き取ったとしても、所有権を完全に使用できない可能性があるため、そのような土地は引き取りの対象外となります。
(3)通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
土地の所有者以外の人によって、土地が利用されている場合、その管理に際して、国と使用者との間で調整が必要になるため、引き取りに対象外となります。
具体的には、通路、墓地、境内、水道用地、用悪水路、ため池などは、第三者も利用したり利害関係がある可能性があるため、国としてはそこまでの調整をしてまでは引き取らないということです。
(4)土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
特定有害物資(カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、ヒ素、ふっ素、ほう素、及びその化合物で環境省令の定める基準値を超えるもの)により汚染されている土地は、その管理や処分に制約が生じ、汚染の除去のために多大な費用が掛かるため、国は引き取ってくれません。そのようなリスクは、汚染させた側が負担するべきだといえますので、当然といえば当然かと思います。
(5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
隣接する土地の所有者との間で所有権の境界が争われている土地や、申請者以外にその土地の所有権を主張する者がいる土地などは、国が引き取ったとしても、その後にトラブルや訴訟に発展する可能性があるため、国としては引き取ってくれません。
ここでいう「境界が明らかでない土地」とは、どの程度境界を明らかにすれば良いのかは、やや難しい点かと思います。
国が測量を行う、いわゆる「地籍調査」は、昭和26年から行われており、開始から半世紀以上が過ぎていますが、令和3年度末時点でようやく約50%が完了した状態です。地籍調査が行われていない土地は、境界が曖昧であるといわざるをえないと個人的には思います。
ただし、過去の土地の売買や、住宅の建築、土地の分筆や道路が通ったなどの出来事の際に、民間や公共工事で測量をしている可能性があります。
そのような場合、現地に境界標が残っていたり、地積測量図が法務局に残っている可能性があります。
国庫帰属制度としては、“測量や境界確認書の提出まで求めるものではありません”と制度の概要書に書いてあるため、測量していない土地をわざわざ測量する必要まではないとも読めますが、一方で、“境界について図面で示したり、現地に目印を設置してください”とも記載されているため、結局のところ、正確な境界を把握している必要がありそうです。
また、同時に隣接の土地所有者と境界についての認識に相違がないことも条件ですので、仮に正確な境界を図示したとしても、隣人とトラブルになっていては、国も引き取ってくれません。
この境界の項目に関しては、どこまで正確な境界を求めるのか、制度のパンフレットからは読み取れないため、やや分かりにくい条件かと思われます。
(6)崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
これは、上記の数値の当てはまる、いわゆる崖地は、原則引き取りがなされません。ただし、しっかりと擁壁工事など安全対策が施されている土地であれば、引き取りの可能性はあるかと思われます。
(7)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
工作物とは、土地に定着する人工物のことです。具体的には、門、擁壁、広告塔、煙突、高架水槽、鉄柱、電柱、遊具など様々です。車両については、見かけたことがある方も多いと思います。明らかにエンジンが掛かりそうにないボロボロの車が置かれた土地がたまにありますが、そのような物が置いてある状態では国は土地を引き取りません。樹木も、宅地に倒木の恐れがある樹木が生えていたりするならば、引き取り対象外になりえます。
ただし、一概に工作物や樹木があれば、引き取り対象外というわけではなく、土地の性質に合わせて考慮されるようです。例えば、山林に樹木があるのは当たり前ですし、宅地に安全性に問題のない土留めや柵などがあったとしても、通常の管理や処分を阻害するものでなければ大丈夫ということになります。
したがって、除去が可能な工作物であれば、除去を検討した上で、国庫帰属を再度検討してみても良いかと思います。
(8)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
具体的には、産業廃棄物、屋根瓦などの建築資材、地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片、古い水道管、浄化槽、井戸、大きな石などが挙げられます。土地の表面上、何も無かったとしても、このようなものが地中にある場合は、引き取りは承認されません。
産業廃棄物や建築資材などが埋められている場合は、当然、その責任は埋めた者又はその承継人が負担するリスクと言えますが、古い水道管、浄化槽、井戸や大きな石などは、悪意がなく、地中に内在する可能性があるため注意が必要です。
目に見えない項目であるため、相続で土地を引き継いだ場合、このような地中の物について認識が無いということもあり得るので、その土地が利用されてきた状況や経緯については、できるだけ調べた方が良さそうです。
(9)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
他の土地に囲まれていて公道に通じない、いわゆる袋地や、池や川や水路や崖があって他人の土地を通らなければ公道に通じない土地は、実は、民法上、その他人の土地を通る権利が存在します。
いわゆる「通行権」という権利です。細かい要件などは割愛しますが、この権利が事実上機能しておらず、通行が妨げられている土地については、結局のところ、隣地所有者とその通行権について争わなければならないため、国としては引き取りの対象外としています。
そのほか、第三者によって所有権が妨げられている土地についても、引き取りの対象外となります。具体的には、不法占拠者がいる場合や、隣地から生活排水が流入してきて土地の利用に支障がある場合などが想定されています。
(10)通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地
大きく分けて3つあります。
1つ目は、災害の危険がある土地です。具体的には、土砂の崩壊、地割れ、陥没、水や汚液の漏出などの災害が発生している、または発生するおそれがある土地をいいます。
そういった土地が、周囲の人の生命や財産に損害を与える可能性があり、それらの防止のために対策工事などをする必要のある土地については、国の引き取りの対象外となります。
2つ目は、動物や病害虫の被害のおそれがある土地です。具体的には、スズメバチやヒグマが頻繁に出るような土地で生命の被害が生じる可能性がある、その土地に生息する病害虫により土地の樹木や農作物に被害が生じるおそれがある場合などです。
3つ目は、整備が必要な山林(森林)です。森林として利用されている土地が、その市町村の森林整備計画に定められた造林の樹種や間伐の方法・基準に適合していない場合、
3.まとめ
以上、不要な土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」という制度についての解説でしたが、いかがだったでしょうか。
おそらく皆様が感じた通り、国としては、かなりシビアな条件を設けています。これは、土地に存在する様々なリスクや不利益を国が負担しないための防衛手段であり、土壌汚染や訴訟リスクなどが内在する土地の責任を国に転嫁させるといったモラルハザードを防ぐためでもあります。
いずれにしてもまずは、第三者に相談することが重要かと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご家族の相続について気になった方、ご不明な方は、お気軽にご相談ください。
LEGAL BASE行政書士事務所|先を見据えた戦略を
https://www.office-legal-base.jp/
Open base|note