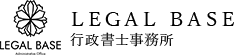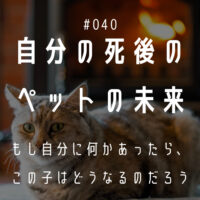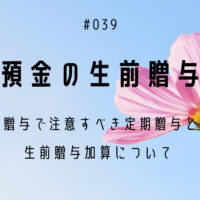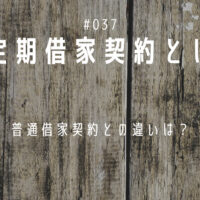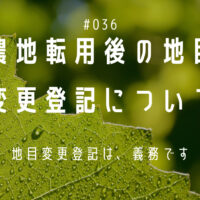#015『自筆証書遺言の要件』
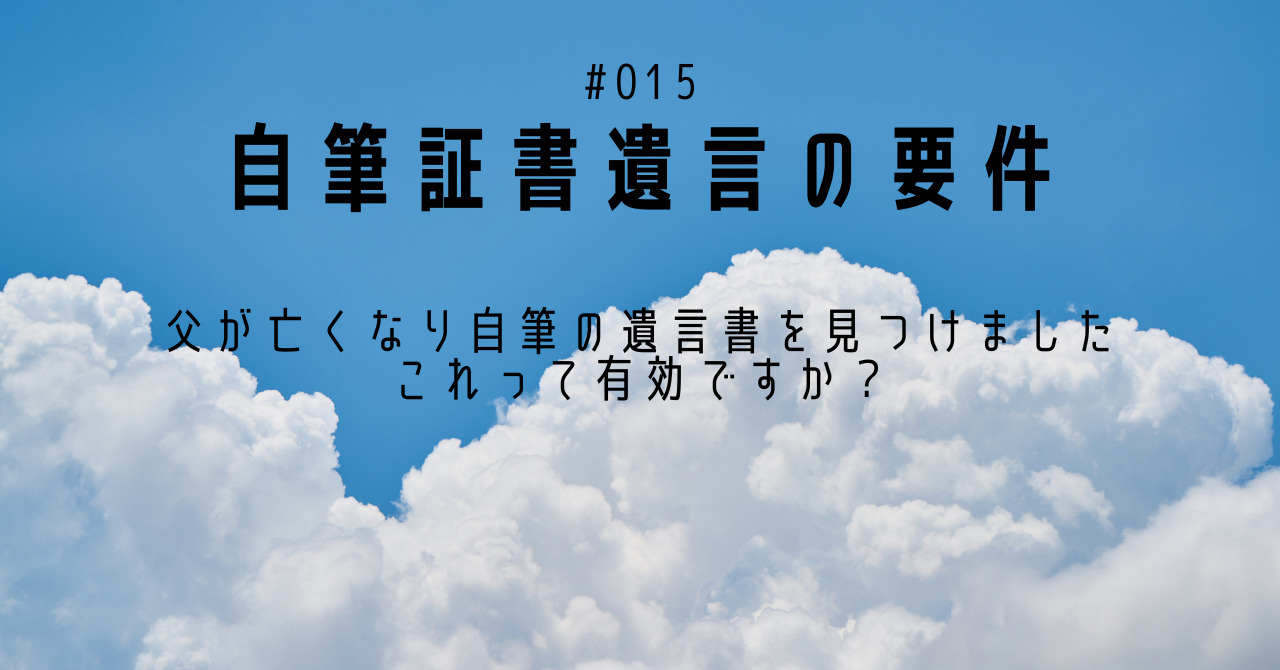
自筆証書遺言は無効?有効性を判断する法的要件とその後の手続き
目次
福岡・博多駅徒歩1分の行政書士事務所 『LEGAL BASE』 代表のSanukiです。
「先日亡くなった父の部屋を整理していたら、封筒に入った手書きの遺言書を見つけた。でも、これが法的に有効なものか分からない…。」
大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、遺言書が見つかると、安堵と同時に多くの疑問や不安が湧き上がってくることでしょう。特に、ご自身で書かれた「自筆証書遺言」は、手軽に作成できる反面、法律で定められた厳格な要件を満たしていないと「無効」になってしまうケースが少なくありません。
もし遺言書が無効になれば、故人の最後の想いは実現されず、相続人間での話し合い(遺産分割協議)が必要となり、時としてトラブルに発展することもあります。
父が自分の為に自筆証書遺言を残していたものの法的要件を満たしておらず、全く面識が無い父の先妻との子らと遺産分割協議をしないといけなくなった、というご相談もありました。
この記事では、相続問題に直面し、自筆証書遺言の有効性で悩んでいる方のために、以下の点を詳しく解説します。
- 自筆証書遺言が有効になるための法的要件
- 遺言書を発見してから、まずやるべきこと
- 遺言が「有効」または「無効」だった場合の具体的な手続きの流れ
- 困ったときの専門家の選び方
そもそも自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者本人が、その全文、日付、氏名を自ら書き、押印して作成する遺言書のことです。公証役場で作成する「公正証書遺言」とは異なり、費用がかからず、証人も不要で、いつでも手軽に作成できるのがメリットです。
しかし、その手軽さゆえに、法律で定められた形式を守れていないことが多く、有効性が争われやすいという大きなデメリットも抱えています。
その遺言、有効ですか?遺言書の要件7つ
見つけた自筆証書遺言が法的に有効かどうか、7つのポイントにまとめてあります。一つでも欠けていると、原則としてその遺言書は無効となってしまいます。
✅ 1. 全文が本人の「自筆」か?
原則として、遺言の本文すべてが遺言者本人の手書きでなければなりません。
- NG例: パソコンやワープロで作成されている、他人による代筆。
- 【例外】財産目録: 2019年の法改正により、相続財産を一覧にした「財産目録」については、パソコンでの作成や、通帳のコピー・登記事項証明書などを添付することが認められました。ただし、その目録の全ページに遺言者本人の署名・押印が必要です。
✅ 2. 「日付」が明確に記載されているか?
遺言がいつ作成されたかを特定するため、日付の記載は必須です。
- OK例: 「令和7年7月10日」
- NG例: 「令和7年7月吉日」、日付の記載がない。
- 日付が特定できない「吉日」などの記載は無効です。実際に「吉日」と書かれた遺言書を目にしたことがありますが、これは要件を満たしません。
✅ 3. 「氏名」が自署されているか?
遺言者本人を特定するため、氏名の自署が必要です。
- 戸籍上の氏名で書くのが最も確実です。
- ペンネームや通称でも、社会的にその個人を特定できるものであれば有効と認められるケースもありますが、争いの種になりやすいため注意が必要です。
✅ 4. 「押印」があるか?
氏名の後に押印が必要です。
- 認印や拇印(指印)でも法律上は有効とされていますが、本人が押したことの証明が容易な実印であることが最も望ましいです。
✅ 5. 訂正方法が正しいか?(加除訂正)
もし内容に訂正や追加がある場合、法律で定められた厳格な方式を守る必要があります。
- 正しい訂正方法:
- 訂正したい箇所を二重線などで消す。
- その近くに正しい文言を記入する。
- 遺言書の余白などに「〇字削除、〇字加入」などと変更内容を書き加える(付記)。
- その付記部分に署名し、押印する。
- この方式に従っていない訂正は、その部分が無効となります。修正テープや修正液の使用では訂正は認められません。
✅ 6. 遺言者に「遺言能力」はあったか?
遺言書を作成した当時、遺言者に十分な判断能力(遺言能力)があったことが前提となります。
- 重度の認知症や精神上の障害により、自分がした遺言の結果を理解できない状態で作成された遺言は、後から無効だと主張される可能性があります。医師の診断書などが証拠となることがあります。
✅ 7. 「共同遺言」ではないか?
あまり考えにくいケースだとは思いますが、法律では、2人以上の人が1つの書面で共同して遺言をすることを禁止しています。
- NG例: 夫婦が連名で1通の遺言書を作成している。
- 必ず一人一通、別々に作成する必要があります。
遺言書を見つけたら、まずやるべきこと
封筒に入った自筆証書遺言を見つけたら、中身が気になっても自分で開封してはいけません。遺言書は、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きを経る必要があります。
検認前に開封してしまうと、5万円以下の過料(罰金のようなもの)に処せられる可能性があります。また、他の相続人から「内容を改ざんしたのではないか」と疑われる原因にもなりかねません。
家庭裁判所での「検認」手続き
検認とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など、その時点での遺言書の客観的な状態を確定させ、偽造・変造を防ぐための手続きです。
検認は、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。 あくまで遺言書の現状を保全するための手続きです。形式不備で無効な遺言でも検認は行われますし、検認を経たからといってその遺言が有効だと確定するわけではありません。
<検認手続きの流れ>
- 申立て: 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認の申立てを行います。
- 必要書類の準備: 申立書のほか、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。
- 相続人への通知: 家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が送られます。
- 検認期日: 裁判所で、申立人や相続人の立会いのもと、裁判官が遺言書を開封し、内容を確認します。
- 検認済証明書の申請: 検認が終わると、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約といった、その後の相続手続きに必要となる「検認済証明書」を申請・取得します。
※ただし、法務局で遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」を利用して作成された遺言書の場合は、この検認手続きは不要です。
遺言が「有効」な場合のその後の流れ
検認手続きが終わり、遺言書の形式に不備がなく有効と判断される場合、原則としてその遺言の内容に従って相続手続きを進めます。
- 遺言執行者の確認: 遺言書で「遺言執行者」が指定されているか確認します。指定があれば、その人が中心となって手続きを進めます。指定がなければ、相続人や利害関係者が家庭裁判所に選任を申し立てることもできます。
- 遺言内容の実現: 遺言執行者または相続人が、遺言書と検認済証明書(または遺言書情報証明書)を使って、不動産の名義変更、預貯金の解約・名義変更などの手続きを行います。
遺留分について たとえ有効な遺言書があっても、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)には、最低限の遺産を取得できる権利「遺留分」が保障されています。もし遺言の内容が自分の遺留分を侵害している場合、その相続人は遺産を多く受け取った他の相続人に対し、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
遺言が「無効」だった場合・内容に争いがある場合
要件を精査した結果、形式不備で遺言が無効である可能性が高い場合や、検認後に遺言の有効性を争う相続人がいる場合はどうなるのでしょうか。
遺言が無効の場合 → 遺産分割協議へ
遺言が無効となると、「遺言はなかった」ことになります。その場合、遺言書が無かった場合と同様、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合って決める必要があります。
話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。この協議書が、その後の相続手続きで必要になります。
話し合いがまとまらない場合 → 調停・審判へ
相続人間で意見が対立し、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停委員を介して話し合いを進めますが、それでも合意に至らなければ、自動的に「遺産分割審判」に移行し、裁判官が遺産の分け方を決定します。
遺言の有効性を争う場合 → 遺言無効確認訴訟へ
検認が終わった後でも、「この署名は本人の筆跡ではない」「遺言能力がない状態で書かれたはずだ」といった理由で遺言の有効性そのものに疑義がある場合は、地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」という裁判を起こして、その有効性を争うことになります。
まとめ:不安なときは、まず専門家へ相談を
自筆証書遺言を見つけたとき、その後の手続きは複雑で、法的な知識が求められる場面が多々あります。
- 遺言書が有効か無効か、自分では判断がつかない
- 相続人の間で意見が対立している、揉めそうだ
- 手続きが複雑で、何から手をつけていいか分からない
- 遺言の内容に納得がいかない
一つでも当てはまる方は、問題を深刻化させないためにも、できるだけ早い段階で我々専門家に相談することをお勧めします。家族間で揉めそうな関係、あるいは既に揉めている場合は弁護士が良いでしょう。関係性が良好な場合は、行政書士または司法書士で構いません。
故人が遺してくれた大切な想いを巡って、家族が争うことほど悲しいことはありません。円満な相続を実現するために、この記事がお役に立てれば幸いです。
LEGAL BASE行政書士事務所|先を見据えた戦略を
https://www.office-legal-base.jp/
Open base|note
https://note.com/openbase